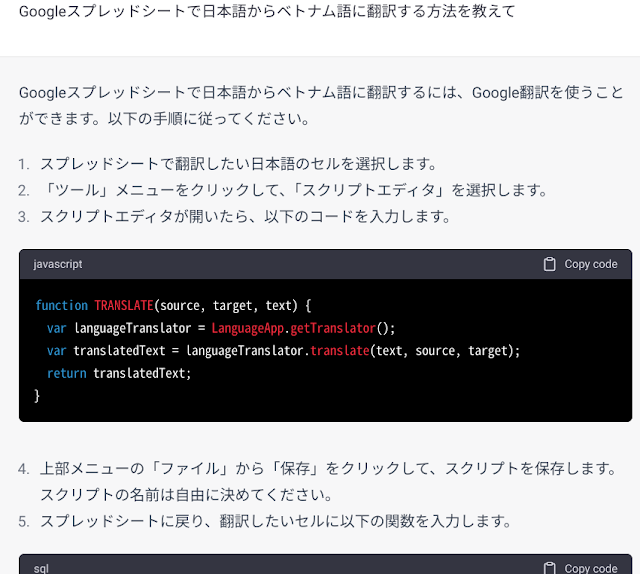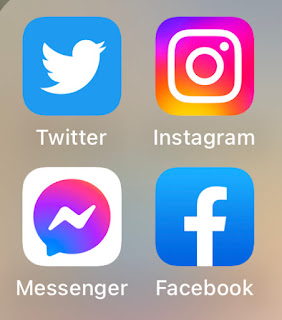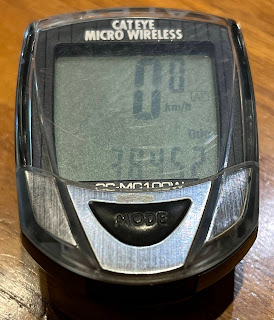Darlinと叫んで思ったこと

『歌ってみた』で吉川晃司の『せつなさを殺せない』を歌ってみて、頻繁にDarlinと歌う(叫ぶ)のが印象的なのだけど、吉川晃司の歌で出てくるDarlinは女性の最愛の人を意味しており、男性から女性に対する呼びかけで使われている。 【歌ってみた】『せつなさを殺せない / 吉川晃司』 歌詞の世界では昔からダーリン(Darlin / Darling)は男性から女性への呼びかけで使われていたけど、90年代後半以降ではそんなに聞かれなくなった気もする。 Darlinは男性から女性、女性から男性、どちらにも使う言葉なのだけど、日本では女性が彼氏に対して使われることが多く、男性が女性に対して使うと変な顔をされる事がある。昔、彼女の事をダーリンがといったら意味が通じなかった。 Wikipediaにも載っているけど、「ダーリン」が男性に対する呼称だと勘違いが広まったのは昔放送されていた海外ドラマの『奥様は魔女』で主人公の旦那さんの名前がダーリンだったことが大きいようだ。 Darrinなので綴も発音も違うのだけどカタカナにしてしまうと同じダーリンになってしまう。 『奥様は魔女』の次に勘違いを広めたのはアニメ『うる星やつら』だと思われる。 ヒロインの宇宙人ラムは「ダーリン」が旦那を意味する言葉だと思っており、常に主人公あたるの事をダーリンと呼んでいる。これは『奥様は魔女』で広まった勘違いが影響しているのだろう。 昔、好んで児童文学を読み漁っていた頃、主人公の少女がDarlinと呼ばれるのが嬉しいというセリフがあって、とても印象的だった。欧米の少女が主人公の児童文学であるのは間違いないけど、なんて本の誰が言ったセリフかは過去の読書感想文を調べてみても出てこなかったのでよくわからない。 ただ、女性が男性に言われて嬉しい言葉というのが日本で広まっている「ダーリン」の印象とは全然違ったので、Darlinという言葉を意識するきっかけになった。 男性アーティストが女性に対する呼びかけとしてDarlinを使う最近の事例があるかどうかわからないけど、今年発売されたMrs. Green Appleの『ダーリン』は「 一人じゃないっていう意味を込めて、僕はこの曲に『ダーリン』というタイトルを付けました。」という記述をみかけた。 この「ダーリン」という曲、タイトルはカタカナだけど、歌詞ではDarlin...